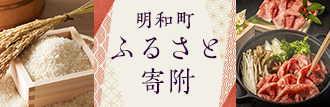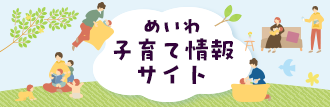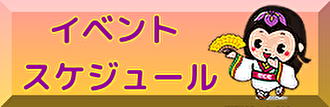明和町手話言語条例
言語は、お互いの意思疎通を図り、人間が知識を蓄え、文化を創造する上で欠かすことのできないものであり、人類の発展に大きく寄与してきました。
手話は、手指や体の動き、表情を使って視覚的に表現する言語です。
ろう者の方々は、物事を考え、コミュニケーションを図り、お互いの気持ちを理解し合うために、また、知識を蓄え文化を創造するために必要な言語として手話を大切に育んでこられました。
しかしながら、これまで手話が言語として認められてこなかったことや、手話を使用できる環境が整えられていなかったことなどから、ろう者の方々は、必要な情報を得られない、周囲とのコミュニケーションを取れないなど、多くの不便や不安を感じながら生活されてきたところです。
こうした中、「障害者の権利に関する条約」や「障害者基本法」において、手話が音声言語と同等の言語として位置付けられましたが、いまだ手話に対する理解及びその普及は、十分とはいえない状況にあります。
そこで、手話が言語であるという認識に基づき、手話の理解に努め、手話を使って安心して暮らすことができ、お互いに助け合い、支え合うことができる明和町を目指し、この条例を施行いたしました。
町民の皆さまにおかれまして、手話を言語として認識し、手話に対するご理解ご協力をお願いいたします。
令和6年12月11日 明和町
ろう者とは
この条例では、聴覚障がい者のうち、「手話」を言語として日常生活や社会生活を送っている人を指します。生まれたときから聞こえず、日本語とは異なる言語である「手話」を第一言語として使っている人はもちろん、難聴者や中途失聴者で、「手話」を学び始め、生活を営んでいる人も含みます。(聴覚障がい者の中には、手話を使わない方も多くいます。こうした方々とは、筆談・口話等によるコミュニケーションや要約筆記による情報提供等を行います。)
手話とは
ろう者がコミュニケーションを図るため、手や指、表情等を用いて豊かに表現する視覚的な「言語」であり、日本語とは異なった独自の文法をもっています。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉総合支援課 障がい福祉係
〒515-0332 明和町大字馬之上945番地
電話番号:0596-63-5461
ファックス:0596-52-7137
お問い合わせはこちらから