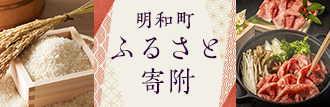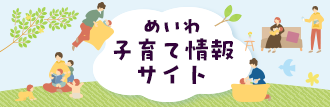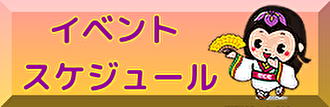福祉医療費助成制度について
障がい者・一人親家庭等・子どものみなさんが医療機関で診療を受けた際の医療費の保険適用分全額相当またはその一部を助成する制度です。
子ども医療費
本町に住所を有する15歳以下の子どもの医療費を助成します。
出生時や転入時に申請してください。
対象者(以下すべてに該当する場合)
- 15歳までの子ども(15歳になった日以降の最初の3月31日まで、4月1日生まれの人は前月末日まで)
- 保護者が下記所得制限内であること
- 健康保険(国民健康保険または社会保険等)をお持ちの方
- 他の福祉医療費助成を受けていない方
- 生活保護法による保護を受けていない方
| 税法上の扶養親族 | 保護者所得額 |
|---|---|
| 0人 | 622万円 |
| 1人 | 660万円 |
- 以降、扶養親族の人数が1人増えるごとに38万円を加算
- 老人扶養者1人につき6万円加算
ひとり親家庭等医療費
本町に住所を有する18歳以下の子どもと、その子どもを養育するひとり親家庭等の母または父の医療費を助成します。
対象者(以下すべてに該当する場合)
- 18歳までの子ども(18歳になった日以降の最初の3月31日まで、4月1日生まれの人は前月末日まで)とその子どもを養育する母または父
- 母又は父及び養育者等が下記所得制限内であること
- 健康保険(国民健康保険または社会保険等)をお持ちの方
- 他の福祉医療費助成を受けていない方
- 生活保護法による保護を受けていない方
| 税法上の扶養親族 | 本人所得額(母又は父) | 養育者・扶養義務者所得額 |
|---|---|---|
| 0人 | 208万円 | 236万円 |
| 1人 | 246万円 | 274万円 |
- 以降、扶養親族の人数が1人増えるごとに38万円を加算
- 本人(母又は父)の場合、老人扶養者1人につき10万円、特定扶養者1人につき15万円加算
- 養育者・扶養義務者(祖父母、おじ・おば等)の場合、老人扶養者1人につき6万円加算、ただし扶養親族が老人扶養だけの場合は1人を除いた老人扶養として加算
障がい者医療費
本町に住所を有する障がいを持つ方の医療費を助成します。
ただし、精神障害者保健福祉手帳1級の方は通院分のみ、2級の方は通院分の2分の1相当額の助成となります。
対象者(以下すべてに該当する場合)
- 次の表のいずれかであること
身体障害者手帳の方 1級から4級 療育手帳の方 A1最重度、A2重度、B1中度、B2軽度 精神障害者保健福祉手帳の方 1級又は2級 - 本人及び配偶者、扶養義務者が下記所得制限内であること
- 健康保険(国民健康保険または社会保険等)をお持ちの方
- 他の福祉医療費助成を受けていない方
- 生活保護法による保護を受けていない方
| 税法上の扶養親族 | 本人所得額 | 配偶者及び 扶養義務者所得額 |
|---|---|---|
| 0人 | 366万1千円 | 628万7千円 |
| 1人 | 404万1千円 | 653万6千円 |
- 以降、扶養親族の人数が1人増えるごとに38万円を加算
- 本人の場合、老人扶養者1人につき10万円、特定扶養者1人につき25万円加算
- 配偶者・扶養義務者(父母、兄弟等)の場合、老人扶養者1人につき6万円加算、ただし扶養親族が老人扶養だけの場合は1人を除いた老人扶養として加算
窓口無料化(現物給付)
15歳までの子ども(15歳になった日以降の最初の3月31日まで、4月1日生まれの人は前月末日まで)の医療費について、窓口負担の無料化(現物給付)を県内医療機関で実施します。
窓口無料化に対応していない医療機関もありますので、受診の前に医療機関等へご確認ください。
対象(以下すべてに該当する場合)
- 福祉医療費の受給資格がある15歳までの子ども(15歳になった日以降の最初の3月31日まで、4月1日生まれの人は前月末日まで)
- 県内の医療機関(医科・歯科・調剤薬局・訪問看護ステーション)での、保険適用となる医療費であること
- 受診時に福祉医療費受給資格証(現物給付用)を提示すること
医療費助成決定通知書の送付について
子ども、障がい者、ひとり親家庭等医療費助成で窓口負担なし(現物給付)の場合は、内訳が記載された医療費助成交付決定通知書(ハガキ)の送付はしておりません。詳しくは下記をご覧ください。
現物給付対象者への医療費助成交付決定通知書送付の廃止について
手続きに必要なもの
- 対象受給者の健康保険の加入状況がわかるもの(保険情報のお知らせなど)
- 口座情報がわかるもの(通帳またはキャッシュカードなど)
- 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
- 同意書(父・母の自署が必要)
- 代理人申請の場合は委任状
委任状(Excelファイル:30.1KB)
受診から助成までの流れ
県内医療機関の場合
- 医療機関の窓口で、健康保険証がわかるもの(マイナ保険証等)と受給資格証を提示してください。提示することで、医療機関より領収証明書が明和町へ送られます。
医薬分業の医療機関で診療を受け、院外の調剤薬局で薬をもらった場合は、医療機関と調剤薬局それぞれに受給資格証を提示してください。 - 受診した医療機関の窓口等で医療費(各自の健康保険で定められた割合の自己負担金)を支払っていただきます。
- 後日(診療月の3~4ヵ月後)、助成金として届出されている口座へ振り込みを行います(償還払い方式)。
- 15歳までの子どもに対しては、窓口で受給資格者証(現物給付用)を提示することで支払いが無料(現物給付)となります。
- 後期高齢者医療制度に加入の方は受給資格証がありません。加入されている健康保険が分かるもの(マイナ保険証等)をご提示ください。
県外医療機関の場合
明和町が発行した福祉医療費助成受給者証は使用できません。
受診した病院等で発行された領収書(保険適用・適用外の分かるもの)を、1か月分まとめて提出してください。
https://logoform.jp/form/YEKu/1234668

補装具を作った場合
補装具(コルセットや小児弱視等治療用眼鏡など)を作った場合は、下記を持参し申請してください。
- 医師からの意見書又は装具装着証明書(補装具を必要とするとの医師からの書類)
- 保険給付支給決定通知(加入する保険組合から給付されることが分かる書類)
- 補装具の領収書
https://logoform.jp/form/YEKu/1234668

助成の対象とならないもの
次のものは医療費助成の対象となりません。
- 入院時の食事療養にかかる標準負担額
- 保険適用とならないもの(健康診査、予防接種、差額ベッド料など)
- 保育所、幼稚園、認定こども園、学校でのけがや病気による診療で、日本スポーツ振興センター災害共済の給付対象となるもの(受給資格証は使用しないでください。先に福祉医療費の助成を受けた場合は返還していただくこととなります。)
- 交通事故など第三者行為による診療となるもの(受給資格証は使用しないでください。先に福祉医療費の助成を受けた場合は返還していただくこととなります。)
- ご加入の健康保険で高額療養費、付加給付金に該当する場合は、その金額
健康保険加入状況が変更となった場合
健康保険加入の状況が変更となった場合は、速やかにご申告ください。
【窓口申請】
下記の持ち物を準備の上、ご来庁ください。
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
・新しい保険加入情報がわかるものと(資格確認書等)
・委任状(代理人が手続する場合)
【オンライン申請】
本人確認書類、新しい保険情報がわかるものをお手元にご準備の上、下記URLまたはQRコードを読み込み、申請してください。
代理人が申請する場合は、オンライン申請ができません。
窓口申請となりますので、ご注意ください。
https://logoform.jp/form/YEKu/1312051

振込指定口座の変更について
福祉医療費助成の振込指定口座変更を希望される方は、速やかにご申請ください。
≪注意事項≫
・申請日によっては、直近の振込日に間に合わない場合がございます。ご了承ください。振込日は原則、月末です。ただし、月末が土日祝日の場合は、翌営業日となります。 審査が完了しましたら、決定通知書(ハガキ)を送付いたしますので内容をご確認ください。
※現物給付(窓口無料化)の場合は、決定通知書の発送はございません。
【窓口申請】
下記の持ち物を準備の上、ご来庁ください。
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
・福祉医療受給資格者証(後期高齢者医療保険加入の方は発行しておりません。)
・登録希望の銀行口座情報がわかるもの(通帳等)
・委任状(代理人が申請する場合)
【オンライン申請】
本人確認書類と銀行口座情報がわかるものをお手元にご準備の上、下記URLまたは、QRコードを読み取り、ご申請ください。
代理人が申請する場合は、オンライン申請ができません。
窓口申請となりますので、ご注意ください。
https://logoform.jp/form/YEKu/1312010

受給資格者証の再発行について
受給資格者証をなくしてしまった、または破れてしまった場合、再発行することができます。
再発行を希望される方は、下記のいずれかでご申請ください。
≪注意事項≫
・後期高齢者医療保険加入の方は、受給資格者証を発行しておりません。
【窓口申請】
下記持ち物を準備の上、ご来庁ください。
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
・委任状(代理人が申請する場合)
【オンライン申請】
本人確認書類をお手元にご準備の上、下記のURLまたはQRコードを読み取り、ご申請ください。
≪注意事項≫
・受給資格者証の受取は福祉総合支援課の窓口になります。
・受取希望日に来庁されなかった場合(変更の連絡がなかった)は、申請を取り下げ させていただきます。
取り下げとなった場合は、再度ご申請が必要となりますのでご了承ください。
https://logoform.jp/form/YEKu/1312057

送付先変更届について
受給資格者本人がご事情(例:施設入所・介護・出産・出張のためにしばらく自宅を不在にする、認知症等により書類の管理が困難であるなど)により住民票と異なる住所地へ送付を希望する場合、ご提出ください。
送付先変更が不要になった場合は、必ず解除のために再度、送付先変更届をご提出ください。
https://logoform.jp/form/YEKu/1237516

その他注意事項
手続き時
申請が遅れた場合(資格取得可能時から1カ月以上経過)の受給開始時期は申請月の初日からとなります。遅延なく申請されることをおすすめします。
受診時
- 受診時に受給資格証を提示できなかった場合は、窓口で医療費を支払うことになりますが、後日受給資格証を医療機関に提示すれば、償還払い方式で助成します。
- 町外への転出などで受給資格を喪失した後は、受給資格証は使用できません。速やかに返還してください。資格喪失後に使用した場合は、明和町への返金が発生しますのでご注意ください。
- 公費負担医療制度(小児慢性特定疾病や育成医療など)の受給者証を持っている人は、窓口で提示してください。公費負担医療制度を利用すると、患者が負担する医療費の額を低く抑えることができ、その自己負担額が医療費助成の対象となります。窓口無料となっても、公費負担医療制度の対象となる場合は、この制度を利用してください。
資格等
- 氏名、住所、加入医療保険、振込先口座に変更があった場合は、すみやかに変更手続きをしてください。
- 転出、死亡等により受給資格を失ったときは、速やかに受給資格証の返還と資格喪失の手続きをしてください。
- 受給資格更新は毎年9月になります。前年の所得により受給資格の有無を判定し、受給資格証を郵送で送付します。有効期限切れの受給資格証は返還するか、各自で破棄してください。
- 後期高齢者医療保険に切り替わる75歳の方の受給資格証の期限は、誕生月までとなります。以降は加入している保険が分かるもの(マイナ保険証等)の提示だけで医療費が助成されます。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉総合支援課 福祉総務係
〒515-0332 明和町大字馬之上945番地
電話番号:0596-52-7115
ファックス:0596-52-7137
お問い合わせはこちらから