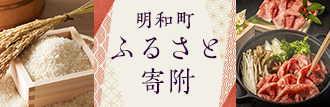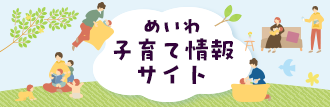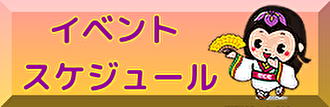明和町の伝統工芸
御糸織
松阪商人が江戸時代に広めた松阪もめんは縦縞の柄が特徴です。それまでの織物は紺色一点張りで、縦縞は粋が誇りの江戸っ子の気風に合い、安くて丈夫なため、一躍大流行しました。歌舞伎役者が縞の着物を着ることを今でも「マツサカを着る」と言うほど、縞柄といえば松阪もめんが代表的な存在でした。
この松阪もめん、実は現在も明和町で製造されており、「御糸織り」の名称で受け継がれています。明和町の「御糸織物工場」では植物の藍で糸を染めて、機械で反物を織るという、全国でも珍しい一貫体制で生産しています。染色し天日干しを行い、美しい藍色の糸ができあがるのはまさに職人技。単に“藍色”“縦縞”といっても、色の濃淡や線の太さなど、デザインのバリエーションはとっても豊富です。




三忠の擬革紙
江戸時代の貞享元年(1684年)、みしま屋忠次郎は、革の風合いを紙で表現した擬革紙を考案しました。神聖な神宮内へ動物の革を用いた製品を身に着けたままお参りすることは良くないとされ、擬革紙で作られた煙草入れなどは、伊勢神宮へお参りに訪れた参詣客のおみやげとして大人気となりました。明治になると擬革紙はヨーロッパ・アメリカの博覧会でも絶賛され、大量に輸出され壁紙にも使われました。
かつて擬革紙を製作した伊勢街道沿いの場所には「まちかど博物館」があり、擬革紙でできた製品など貴重な資料が見学できます。




関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
斎宮跡・文化観光課 文化財係
〒515-0321 三重県多気郡明和町斎宮2811
いつきのみや地域交流センター 内
電話番号:0596-63-5315
ファックス:0596-63-5316