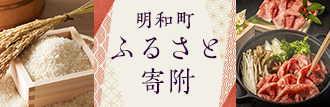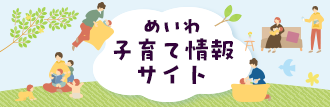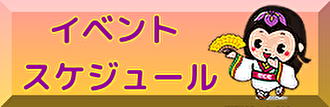児童手当の制度改正について(令和6年10月分から)
・出生、転入出、その他の手続きについては「児童手当の必要な手続き等について」をご覧ください。
・制度改正の概要についてはこちらをクリック
・制度改正に伴う手続きについてはこちらをクリック
※こども家庭庁ホームページで制度改正の詳細やQ&Aが掲載されておりますので、併せてご覧ください。
※令和6年9月20日に高校生年代および大学生年代を養育していると思われる方に通知をしました。
※通知が届いた場合であっても、大学生年代の子のみを養育している方は、制度改正後の支給対象には該当しません。ご了承ください。(町で把握できない子を養育している場合等を考慮し、皆様に通知しています。)
令和6年10月分(令和6年12月10日支給予定)から、児童手当制度が改正されます。
※令和6年10月10日に支給(予定)される児童手当(令和6年6月・7月・8月・9月分)については、制度改正前の支給額を支給します。制度改正後の最初の支給は令和6年12月10日(予定)です。
支給日・支給方法
偶数月(2、4、6、8、10、12月)の10日(当日が土曜・日曜・祝日の場合は、前後する場合がございます。)に、指定の受給者名義の口座に振込みます。
- 2カ月に一度まとめての支払いになります。
- 支払いの通知はしませんので、支給日以降に通帳でお確かめください。
- 金融機関によって振込時間が異なります。
■児童手当支払通知書の廃止について
令和6年10月の制度改正に伴い、送付していた児童手当の「支払通知書」については、令和7年10月期分(令和7年8~9月分)から廃止となります。
今後の支給金額等の確認は、支払日(偶数月10日)以降に通帳の記帳等によりご確認ください。
児童手当制度改正の概要について
|
改正前 |
改正後 |
|
|---|---|---|
|
支給対象 |
中学校修了までの児童(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)を養育している方 |
高校生年代修了までの子(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)を養育している方 |
|
所得制限 |
あり |
なし |
|
支給月額 |
【3歳未満】 |
【3歳未満】 |
|
第3子以降となる |
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの養育している子のうち、3番目以降 |
22歳に達する日以後の最初の3月31日までの養育している子のうち、3番目以降(親等の経済的負担がある場合) |
|
支給時期 |
年3回(6月、10月、2月) |
年6回(偶数月) |
主な改正内容について
●支給対象年齢の延長
児童手当の支給対象となる子の年齢が、18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)となります。
●所得制限の撤廃
所得の額にかかわらず、児童手当が支給されます。
なお、父母がともにお子さんを養育されている場合は、お子さんの父母のうち、いずれかそのお子さんの生計を維持する程度の高い方(家計の主宰者)に児童手当が支給されます。
●第3子加算の増額
第3子以降の18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)の子は、月額3万円の支給となります。
【第3子加算の数え方(カウント方法)の変更】
多子加算のカウント方法については、現在の18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)を第1子とする扱いを見直し、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの上の子について、親等の経済的負担がある場合は第1子とするカウント方法に変更となります。
●支給月の変更
児童手当の支給月が4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回となります。
現行制度では4か月分の手当を年3回支給していましたが、制度改正後は2か月分の手当が隔月(偶数月)に支給されます。
※制度改正後の最初の支給(予定)日は、令和6年12月10日(火曜日)(令和6年10月・11月分)です。
児童手当制度改正に伴う手続きについて
手続き要否確認フローチャート
今回の児童手当制度改正に伴う、申請手続きの要否及び提出書類について、「フローチャート(PDFファイル:733.4KB)」にてご確認ください。
※大学生年代の子のみを養育している方は、制度改正後の支給対象には該当しません。ご了承ください。(町で把握できない子を養育している場合等を考慮し、皆様に通知をお送りしています。)
受給資格者
受給資格者は、児童の父母等のうち生計中心者(原則、所得が高い者)となります。
※児童が児童養護施設等に入所している場合は、原則として、施設の設置者が受給資格者となります。
申請の提出期限
提出期限:令和6年10月25日(金)※郵送提出の場合、当日消印有効
最終提出期限:令和7年3月31日(月)※郵送提出の場合、必着
・「児童手当認定請求書」の提出が必要な方→下記【ア】、【イ】に該当の方
提出期限までに必要書類が提出されない場合は、12月支給(10月分、11月分)は
ありません。ただし、最終提出期限までに提出があった場合は、令和7年1月以降
に、令和6年10月分から遡って支給します。
・「額改定認定請求書」及び「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が
必要な方→下記【ウ】、【エ】に該当する方
提出期限までに必要書類が提出されない場合は、改正前の対象児童のみに係る
手当額となります。ただし、最終提出期限までに提出があった場合は、令和7年
1月以降に、令和6年10月分から遡って改定差額を支給します。
・最終提出期限を過ぎ、令和7年4月1日以降に提出された場合は、受付した日の
属する月の翌月分からの支給となります。令和6年10月から遡って手当を受ける
ことができませんので、ご注意ください。
申請が必要な方
【ア】: 中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の子を養育している方
【イ】 : 制度改正前において、所得が所得制限の上限限度額を超えたことにより支給対象外となった方(明和町から受給事由の消滅又は却下の通知を受けている方)
【ウ】 : 児童手当等を受給中であるが、多子加算の算定対象児童として登録されていない高校生年代の子を養育している方
※多子加算:父母等が大学生年代以下の子(平成14年4月2日以降に生まれた子)を3人以上養育している場合に3人目以降の子どもの手当額が増額されること
※算定対象児童:児童手当の支払い対象ではないが、児童数にカウントする児童のこと。制度改正前は高校生年代、制度改正後は大学生年代を対象としている。
【エ】:「平成14年4月2日から平成18年4月1日までの生まれ(大学生年代)」の方と、「平成18年4月2日以降の生まれ(支給対象児童)」を含めて3人以上養育している方
(注意1)今回の制度改正に伴い、申請が必要であると思われる方には、児童手当制度改正に関するお知らせ(申請書等同封)を令和6年9月中に発送します。お手元に届きましたら、内容を必ずご確認ください。また、フローチャートをご確認いただき、支給対象であるにも関わらず、9月中にお知らせが届かなかった場合は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
ただし、次の方は明和町からの支給ではないため、各支給元へご確認ください。
| 支給元 | |
|---|---|
|
●公務員 |
職場(勤務先) |
|
●受給資格者が明和町外に |
住民票登録がある自治体 |
【ア】中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の子を養育している方
【イ】制度改正前において、所得が所得制限の上限限度額を超えたことにより支給対象外となった方(明和町から受給事由の消滅又は却下の通知を受けている方)
●提出書類
<記入に必要なもの>
・請求者の個人番号(マイナンバー)
・配偶者の個人番号(マイナンバー)
・請求者名義の口座がわかるもの
※請求者以外の名義の口座はご指定できません。
2.監護相当・生計費の負担についての確認書(該当者のみ)(C)
※「監護相当・生計費の負担についての確認書」は、1人以上の兄姉等(平成14年4月2日から平成18年4月1日までの生まれ)と手当対象児童(平成18年4月2日以降の生まれ)を含めて3人以上養育している場合に限り、「児童手当認定請求書」と併せて提出が必要です。
<記入に必要なもの>
・親等の経済的負担がある18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある兄姉等(平成14年4月2日から平成18年4月1日までの生まれ)の個人番号がわかるもの
3.請求者の健康保険証(該当者のみ)
4.窓口:来庁する方の身分証明書(写し)
郵送:書類を記入する方の身分証明書(写し)
※顔写真付き(マイナンバーカード、運転免許証等)の場合は1種類、顔写真がない場合は2種類必要です。
(注意2)受給者と児童が別の住所であるとき等追加書類が必要な場合がございます。ページ下部の「追加提出書類」をご確認ください。
【ウ】 児童手当等を受給中であるが、多子加算*注意3の算定児童として登録されていない高校生年代の児童を養育している方
●提出書類
※【エ】にも該当する場合は、【エ】の提出書類も併せてご提出ください。
2.窓口:来庁する方の身分証明書(写し)
郵送:書類を記入する方の身分証明書(写し)
※顔写真付き(マイナンバーカード、運転免許証等)の場合は1種類、顔写真がない場合は2種類必要です。
(注意2)受給者と児童が別の住所であるとき等追加書類が必要な場合がございます。ページ下部の「追加提出書類」をご確認ください。
(*注意3):父母等が大学生年代以下の子(平成14年4月2日以降に生まれた子)を3人以上養育している場合に3人目以降の子どもの手当額が増額されること
【エ】 「平成14年4月2日から平成18年4月1日までの生まれ(大学生年代)」の方と、「平成18年4月2日以降の生まれ(支給対象児童)」を含めて3人以上養育している方
●提出書類
※【ウ】にも該当する場合は、【ウ】の提出書類も併せてご提出ください。
※「監護相当・生計費の負担についての確認書」は、1人以上の兄姉等(平成14年4月2日から平成18年4月1日までの生まれ)と手当対象児童(平成18年4月2日以降の生まれ)を含めて3人以上養育している場合に限り、「児童手当認定請求書」と併せて提出が必要です。
<記入に必要なもの>
・親等の経済的負担がある18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある兄姉等(平成14年4月2日から平成18年4月1日までの生まれ)の個人番号がわかるもの
2.窓口:来庁する方の身分証明書(写し)
郵送:書類を記入する方の身分証明書(写し)
※顔写真付き(マイナンバーカード、運転免許証等)の場合は1種類、顔写真がない場合は2種類必要です。
3.委任状(代理人(配偶者含む)が申請する場合のみ)(D)
(注意2)受給者と児童が別の住所であるとき等追加書類が必要な場合がございます。ページ下部の「追加提出書類」をご確認ください。
「児童手当制度改正の概要について」に戻る
「手続き要否確認フローチャート」に戻る
「申請が必要な方」に戻る
【追加提出書類】上記の内容に加えて、以下に該当する方はその他の申立書も必要となります。
受給者と児童が別の住所であるとき
受給者が児童と別居しているが、その児童を監護し、生計を同じくしているときに併せてご提出ください。※こちらに該当する場合は原則窓口受付といたします。
●追加提出書類
<記入に必要なもの>
・児童および配偶者の個人番号がわかるもの
養育している児童が実子以外(孫、甥や姪など)のとき
実子以外(孫、甥や姪など)の児童を監護し、生計を同じくしているときに併せてご提出ください。児童と同一世帯であることが前提です。※こちらに該当する場合は原則窓口受付といたします。
●追加提出書類
離婚協議中により配偶者と別居しているとき
児童と同居している方に優先して支給されますので、併せてご提出ください。詳細は、こども家庭庁Q&Aをご確認ください。※こちらに該当する場合は原則窓口受付といたします。
●追加提出書類
※窓口にてご用意いたします。
2.離婚協議中であることが客観的に証明できるもの(協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状のコピー、調停不成立証明書のコピー等)
留学等により国外に居住している児童を監護・生計を同じくしているとき
児童が海外に住んでいる(日本国内に住所を有しない)場合、その児童の分の手当は原則として支給されません。ただし、児童が留学を理由として海外に住んでいて、要件を満たしている場合は、例外として、その児童の分の手当を受け取ることができます。要件については、こども家庭庁Q&Aをご確認ください。※こちらに該当する場合は原則窓口受付といたします。
●追加提出書類(要件に該当している場合)
2.留学の事実が分かる書類(児童の氏名、留学先の教育機関の名称、留学開始日が掲載されているもの)
3.留学前の国内居住状況がわかる書類(戸籍の附票の写し、国内の学校における在学証明書等)
4.翻訳書(添付書類が外国語で記載されている場合)
「児童手当制度改正の概要について」に戻る
「手続き要否確認フローチャート」に戻る
「申請が必要な方」に戻る
請求書等の様式
A:児童手当認定請求書(様式)(PDFファイル:575.5KB)
B:児童手当額改定請求書(様式)(PDFファイル:365.4KB)
児童手当額改定請求書(記入例)(PDFファイル:955.7KB)
C:監護・生計費の負担についての確認書(様式)(PDFファイル:125.1KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例)(PDFファイル:286.2KB)
E:別居監護申立書(様式)(PDFファイル:110.1KB)
F:児童手当等監護・生計維持申立書(様式)(PDFファイル:368.5KB)
G:児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)(様式)(PDFファイル:159KB)
H:児童手当等に係る海外留学に関する申立書(児童用)(様式)(PDFファイル:190.8KB)
I:児童手当等に係る海外留学に関する申立書(兄姉等用)(様式)(PDFファイル:195KB)
「児童手当制度改正の概要について」に戻る
「手続き要否確認フローチャート」に戻る
「申請が必要な方」に戻る
この記事に関するお問い合わせ先
こども課 こども政策係
〒515-0332 明和町大字馬之上945番地
電話番号:0596-52-7123
ファックス:0596-52-7137
お問い合わせはこちらから