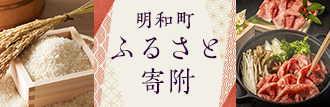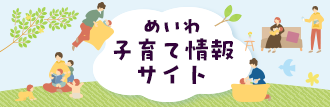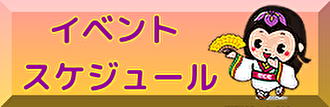斎王ゆかりの地(町外編その1)
今も残る、斎王ゆかりの史跡や神社
その場所に立てば、遙か時の彼方の物語がかいま見えるかもしれません
このコーナーでは、『日本書紀』等のほかに、中世の伊勢伝承である『倭姫命世記』等も参考にしています。そのため、歴史的事実である根拠に乏しい内容も含まれています。
文中の年数等は、『倭姫命世記』などの中世の伝承によるものです。
蛭子神社(えびすじんじゃ/名張市)
倭姫命(やまとひめのみこと)が訪れた市守宮の比定地


倭姫命は、天照大神(あまてらすおおみかみ)を奉じて、大神が鎮まる地を求めて各地をめぐった。この時、大神を一時的に祀った所は、元伊勢と呼ばれて、今でも神社として残っているところがある。
三重県名張市の蛭子神社(えびすじんじゃ)もそのひとつである。名張の市街地の一角、名張川沿いに鎮座するこの神社は、垂仁天皇64年に倭姫命が訪れ、2年間天照大神を祀った伊賀国の市守宮(いちもりのみや)であるといわれている。
また、この蛭子神社はもとは、南1キロメートルほどの中村という地区から移されたといい、毎年2月には「えびす祭」でにぎわう。
そのほかにも、倭姫命が休まれたという名張川の中の岩や、足を洗われたという池など、名張市全域ににいくつもの伝承が残る。また、名張は壬申の乱の際、大海人皇子が通り、川の上にかかる黒雲を見て勝利を占ったという地であり、白い鹿に助けられて川を渡ったという伝説もある。
大来皇女(おおくのひめみこ)が建立した昌福寺(しょうふくじ)といわれる夏見廃寺跡(なつみはいじあと)も、蛭子神社から北東3キロメートルほどの所である。
都美恵神社(つみえじんじゃ/伊賀市)
倭姫命が訪れた敢都美恵宮(あえとみえのみや)の比定地

崇神天皇の58年、垂仁天皇の皇女・倭姫命は、叔母の豊鍬入姫命(とよすきいりひめのみこと)より、天照大神の御杖代(みつえしろ)の役目を受け継ぎ、大神の鎮座される地を求めて旅立った。大和国を出て伊賀国・近江国・尾張国そして伊勢国と至る長い旅の始まりである。(尾張国は『倭姫命世記』にのみ記され、『日本書紀』には記されていない)
伊賀市にある都美恵神社は、伊勢へと至る旅の途中、倭姫命が立ち寄られ、垂仁天皇の2年から2年間大神をお祀りした「敢都美恵宮」といわれている。
伊賀市には、大和地方から伊賀を越え、東海道に合流して江戸へと続く大和街道が通っている。壬申の乱の折、大海人皇子はこの街道の原型にあたる道を通ったといわれている。現在、神社は街道のの近くにあるが、神社から出て街道に沿って少し離れたところに「敢都美恵宮跡」と記された石碑がある。かつての敢都美恵宮は、その石碑からもう少し離れた古宮というところにあり、ある時、土地が陥没したため場所が移され、穴石神社と合祀されたという。
社殿は、高い石垣の上にあり、どことなく城塞のような雰囲気。
斎王の伝説や、街道の歴史が残るこの場所を、ゆっくり旅してみてはいかがだろう。
皇女の森(こじょのもり/伊勢市)
悲劇の斎王・稚足姫皇女(わかたらしひめのひめみこ)ゆかりの場所

宇治乃奴鬼神社跡(遠景(注意)令和3年頃)

宇治乃奴鬼神社跡(近景(注意)平成期)

皇女森跡(伊勢市中村町伝承)
斎王・稚足姫皇女が鏡を埋めて命を絶った場所であるとも、(伊勢参宮名所図会)、倭姫命が天照大神を祀る地を探して訪れた際、猿田彦命が大神を祀るのに良い場所があると申し上げた場所であるとも伝えられている。(伊勢名勝志)
伊勢市楠部町の国道23号と近鉄鳥羽線が交差する付近の水田の中に小さな森のようになって残っている「宇治乃奴鬼神社跡(うじのぬき)」を、現在「皇女の森」と紹介されることがあるが、伊勢市中村町では「皇女の森」は宇治乃奴鬼神社の約150m南方にあったとされる。(中村町文化財保存会だより第6号参照)
また、伊勢神宮から直線距離にして約12キロメートルとやや遠いが、現在の玉城町積良(つむら)、あるいは隣接する矢野地区(式内社田乃家神社がある)も稚足姫皇女の最期の場所であるとする説がある。
一方、盧城部連武彦(いおきべのむらじたけひこ)が殺された盧城河場は、現在の雲出川といわれ、津市白山町には、飛落首(ひひくび)という地名が残り、近くには斎王ゆかりと伝えられる「こぶ湯」がある。
中村町文化財保存会だより第6号 (PDFファイル: 979.4KB)
神山神社(こうやまじんじゃ/松阪市)
飯野高宮(いいののたかみや)の比定地

豊鍬入姫命から御杖代の役目を引き継いだ倭姫命は、伊賀、近江、尾張等を巡り、最後に伊勢国へと至る。この長い御巡幸の旅を記した『倭姫命世記』には、垂仁天皇の22年に「飯野ノ高宮」で4年間天照大神をお祀りしたと記されている。
この飯野高宮ではないかと考えられているのが、松阪市の櫛田川に近い山添町にある神山神社である。現在は山麓にあるが、もともと社は山の上にあったといわれている。
この他にも櫛田川沿いには、神戸神館神社(下村町)、牛庭神社(下蛸路町)など、飯野高宮にかかわる神社や飯野高宮ではないかと考えられている神社がいくつも点在している。
おそらく、飯野高宮に滞在した4年間の間にも、倭姫命は、大神の鎮座するにふさわしい土地を探してまわったことだろう。その伝説が今も櫛田川沿いの神社に残っている。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
斎宮跡・文化観光課 文化財係
〒515-0321 三重県多気郡明和町斎宮2811
いつきのみや地域交流センター 内
電話番号:0596-63-5315
ファックス:0596-63-5316