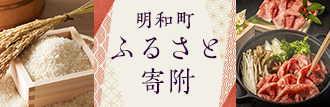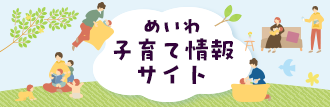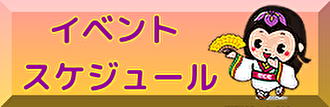罹災証明書と罹災届出証明書について
町では、風水害や地震等の自然災害によって家屋等に被害があった場合、被災者支援措置制度を受ける際や保険金等の請求に必要となる「罹災証明書」「罹災届出証明書」を交付しています。
火災による罹災証明書については、松阪地区広域消防組合の消防本部予防課【TEL:0598-25-1412】にお問い合わせください。
被災状況の写真撮影・保存のお願い
罹災証明書の交付には、職員による住家の被害認定調査(現地調査)が必要となります。しかし、調査の前に建物の除去や被害箇所の特定ができなくなるような修理、片付け等を行ってしまいますと調査が困難となります。
そのため、あらかじめ被災状況を写真に撮影し保存していただくようお願いします。以下の動画及びリーフレットを参考としてください。
【動画】災害で住まいが被害を受けたとき 最初にすること ~被害状況を写真で記録する~
【リーフレット】内閣府 住まいが被害を受けたとき 最初にすること
証明書の種類
罹災証明書
「罹災証明書」とは、自然災害による住家(居住のために使用している建物)の被害について、町が被害認定調査を行い、被害の程度を証明するものです。
罹災証明書の対象
・住家(災害発生時において、現実に居住のため使用している建物)
被害程度の区分
|
被害の程度 |
損害割合 |
|
全壊 |
50%以上 |
|
大規模半壊 |
40%以上50%未満 |
|
中規模半壊 |
30%以上40%未満 |
|
半壊 |
20%以上30%未満 |
|
準半壊 |
10%以上20%未満 |
|
準半壊に至らない (一部損壊) |
10%未満 |
※このほか、必要に応じて浸水区分(床上浸水・床下浸水)を証明する場合があります。
罹災届出証明書
「罹災届出証明書」とは、自然災害による建物、構築物、動産の被害について、被害の程度ではなく、被害の届出があったことを証明するものです。 現地調査は行いませんので、被害の状況が確認できる写真が必要です。
罹災届出証明書の対象
・事業所、店舗、倉庫など、住家以外の建物
・カーポート、フェンス、車両、家財など
申請方法等
罹災証明書
申請に必要なもの
・罹災証明申請書
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
・被害の状況が確認できる写真等(自己判定方式※の場合)
・代理人が申請する場合は、委任状
※被害が軽微な場合の「自己判定方式」について
住家の損害割合が明らかに10パーセント未満であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という調査結果に同意できる場合、調査員による現地調査は行わず、写真により被害認定を行います。 写真は、住家の全景(可能であれば4方向から)と被害を受けた箇所について、印刷したものを提出してください。
申請の受付期間
災害の発生した日から90日以内に申請してください。
罹災届出証明書
届出に必要なもの
・罹災届出書
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
・被害の状況が確認できる写真等(車両の場合は、ナンバープレートを確認できる写真をご用意ください。)
・代理人が届出する場合は、委任状
なお、災害発生から時間が経過すると被害の程度を確認することが困難になることから、被災から90日を経過した場合は、住家についても原則として罹災届出証明書を交付します。
被害認定再調査申請書について
罹災証明書により証明された被害の程度について、相当の理由がある場合は当該証明書の交付を受けた翌日から起算して60日以内に再調査を申請することができます。
申請にあたっての注意点等
・証明書の交付に係る手数料は無料です。
・現地調査や交付事務の都合等により、証明書の即時交付はできませんのでご了承ください。
・災害の規模により町内で被害が多く発生した場合、申請窓口が混雑するほか、現地調査や証明書の交付に時間がかかる場合があります。
・交付できる枚数は、原則として災害毎に1世帯1枚です。複数必要な場合は、申請者にてコピーして使用してください。
申請様式等
世帯主及び同世帯の親族の方以外が申請する場合は委任状が必要となります。 代理人の場合は委任状および代理人の方の本人確認書類をご持参ください。
罹災証明書
罹災証明申請書【記入例】 (PDFファイル: 282.2KB)
罹災届出証明書
被害認定再調査申請書
共通
ぴったりサービスによる罹災証明書の電子申請について
マイナポータルのサービスを利用し、パソコンやスマートフォンから罹災証明の電子申請を行うことができます。
自己判定方式による申請の場合、写真データの添付が必要です。
詳しくは下記リンクをご確認ください。