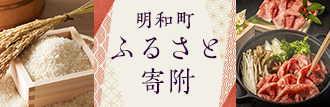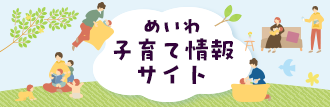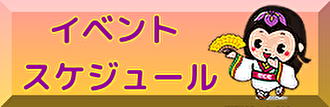防災マップ&防災情報
昨今、南海トラフを震源域とする地震がいつ発生してもおかしくないと言われています。また、地震のみならず、洪水や土砂災害といった風水害による被害も全国各地で発生しています。様々な災害からの被害を最小限におさえるためにも、一人ひとりが防災の知識と心構えを身につけておくことが大切です。
防災に関する情報や、ハザードマップ等をまとめていますので、身の回りにある危険性を知り、災害への備えを強化しましょう。
明和町防災マップ・ハザードマップ
この防災マップは、令和2年3月(櫛田川洪水ハザードマップ及び高潮ハザードマップについては令和2年9月、祓川洪水ハザードマップ及び中川洪水ハザードマップについては令和5年11月)に作成したもので、明和町を襲う可能性のある災害について記したほか、防災・減災に関する知識や、各ご家庭、地域等でおこなっていただく準備・対策等についても記しています。
また、災害種別ごとのハザードマップも作成していますので、ご自宅や勤務先等の災害リスクについて、確認しておきましょう。
明和町防災マップ2020(冊子) (PDFファイル: 15.2MB)
明和町防災マップ2020(避難所・拠点マップ) (PDFファイル: 2.9MB)
明和町防災マップ2020(津波ハザードマップ) (PDFファイル: 2.8MB)
明和町防災マップ2020(大堀川洪水ハザードマップ) (PDFファイル: 3.1MB)
明和町防災マップ2020(笹笛川洪水ハザードマップ) (PDFファイル: 3.2MB)
明和町防災マップ2020(櫛田川洪水ハザードマップ) (PDFファイル: 1.5MB)
明和町防災マップ2020(高潮ハザードマップ) (PDFファイル: 1.3MB)
明和町防災マップ2020(祓川洪水ハザードマップ) (PDFファイル: 4.1MB)
明和町防災マップ2020(中川洪水ハザードマップ) (PDFファイル: 2.9MB)
その他のハザードマップ
「土砂災害ハザードマップ」と「ため池ハザードマップ」についても別途公開しています。
これらのハザードマップは、下記リンク先からご確認ください。
また、液状化危険度分布図についても、三重県ホームページで公開されていますのでご確認ください。
(リンク先:建設課)
(リンク先:産業振興課)
(リンク先:三重県ホームページ)
過去の防災マップ
以前の防災マップは下記リンクをご覧ください。
明和町防災マップ「2009作成(2018一部改訂)」 (PDFファイル: 8.9MB)
明和町防災マップ中国語版(2009作成) (PDFファイル: 7.7MB)
浸水予測図(津波・洪水・高潮)
南海トラフ地震により発生が懸念される津波浸水については、平成26年に三重県が作成した津波浸水想定(理論上最大)が発表されています。
以下のリンク(三重県ホームページ)よりご確認ください。
櫛田川については、上記防災マップに掲載した浸水想定の他に、国土交通省三重河川国道事務所において、想定最大規模等の浸水想定図が新たに作成されています。
以下のリンク(三重河川国道事務所ホームページ)よりご確認ください。
笹笛川については、上記防災マップに掲載した浸水想定の他に、令和元年6月に三重県において、想定最大規模等の洪水浸水想定区域図が新たに作成されています。
以下のリンク(三重県ホームページ)よりご確認ください。
大堀川については、上記防災マップに掲載した浸水想定の他に、令和元年6月に三重県において、想定最大規模等の洪水浸水想定区域図が新たに作成されています。
以下のリンク(三重県ホームページ)よりご確認ください。
高潮については、上記防災マップに掲載した浸水想定の他に、令和2年8月に三重県において、想定最大規模等の洪水浸水想定区域図が新たに作成されています。
以下のリンク(三重県ホームページ)よりご確認ください。
その他の各種ハザードマップについても、三重県のホームページに掲載されています。
以下のリンクよりご確認ください。
防災情報
防災無線
防災無線は、台風などで大きな被害が予想される場合や火災などの緊急情報を無線でお知らせするシステムです。
万一の際は、役場の親局から情報を発信し、ご家庭の戸別受信機と町内の主な箇所に設置された屋外子局から必要な情報をお知らせします。また、平常時は行政や学校などからの案内放送を行っています。防災無線についてのお問い合わせは、総務防災課へ。
地震がおこったら?
突然、グラグラっときたらどうする? 地震から身を守るための10カ条
- わが身の安全を確保!
家の中なら、丈夫な机の下などに隠れる! 揺れがおさまるまで様子を見ます。
海岸や山や急な斜面の近くでは津波や崖崩れの可能性があるので、すぐに避難しましょう。 - すばやく火の始末!
地震に加えて火事まで起こってしまっては大変!
暖房器具やガスコンロなど、火事の元になりそうなものはすぐに火を消しましょう。 - 非常脱出口を確保!
地震が発生したら、玄関などの扉を開けて、非常脱出口を確保しましょう。 - 火が出たらまず消火
万一出火したら、火が大きくならない内に消しましょう。
大声で隣近所に知らせてみんなで協力して消火にあたりましょう。 - あわてて外に飛び出すのは危険!
グラッときてあわてて外へ飛び出すと、瓦や窓ガラスなどが落ちてきて危険です。
大きな揺れがおさまってから、落ちついて行動しましょう。 - 危険な場所は避けて!
狭い路地や塀のそば、崖や川べりは崩れる危険があるので近づかない方が安全です。 - 避難は徒歩で。持ち物は最小限に
避難は必ず徒歩で。自動車は救急救護活動の妨げになります。
持ち物は必要なものだけにして、身軽に行動できるようにしましょう。 - みんなで協力しあって応急処置を
災害が大きくなると負傷者も多くなります。
軽いケガなどは、みんなで協力しあって応急処置をしましょう。 - 正しい情報が大切!
テレビやラジオ、町の防災無線や公的機関の広報などで、情報を確認しましょう。 - 災害現場は危険!
地震で倒れかかった家などに近寄ると、余震などで建物が崩れて大変危険です。
災害復旧作業のさまたげにもなるので、人命救助などの場合を除いては危険な場所に近寄らないようにしましょう。
わが家の安全対策
家の中の安全対策

- 家の中に逃げ場としての安全な空間をつくる
人の出入りが少ない部屋に家具をまとめて置きましょう。無理な場合は、少しでも安全なスペースができるよう、配置替えをしましょう。 - 寝室には家具を置かない
就寝中に地震に襲われると非常に危険です。特に、子供や高齢者、病人などは、倒れた家具が障害になって逃げ遅れる可能性があるので注意が必要です。どうしても置かざるを得ない場合は、倒れてきても下敷きにならない場所で寝ましょう。 - 家具は倒れにくいように配置し、固定する
家具は壁や柱にぴったりつけて置きましょう。下に小さな板などを差し込んで、壁などに寄りかかるようにするとよいでしょう。また、金具や固定器具を使って転倒・落下防止策を万全にしましょう。 - 出入口や通路に物を置かない
玄関や廊下は、イザというときに逃げ場になる大切な場所。出来るだけ家具などを置かないようにしましょう。
地震に備えて非常持出品の準備を
非常持出品の用意のポイント

各自に1個のリュックサックを用意し、それぞれ持ち出しやすい場所に保管をしておきましょう。
| 貴重品 |
現金(要10円玉)、預貯金通帳、印鑑、免許証、権利証書、健康保険証、重要書類の番号を記したもの など |
|---|---|
| 非常食など |
乾パン、クラッカー、缶詰など保存性の高いもの、飲料水(缶やペットボトルのもの)、紙皿、紙コップ、割りばし、ナイフ、缶きり、栓抜き、粉ミルク(赤ちゃん用)など |
| 応急医薬品 |
ばんそうこう、包帯、胃腸薬、消毒薬、傷薬、鎮痛剤、かぜ薬、持病の薬など |
| 生活用品 (必要に応じて) |
衣類(下着・上着・靴下など)、タオル、寝袋、ティッシュペーパー、ウェットティッシュ、軍手、雨具、ライター、ビニール袋、生理用品、紙おむつ、包装用ラップ、使い捨てカイロ、防塵マスク、哺乳びん、母子手帳、予備メガネなど |
| その他 | 携帯ラジオ、懐中電灯、電池など |
地震のとき、こんな場所にいたら!
住宅街にいたら
- ブロック塀や電線などからすぐに離れて安全な場所へ。
- 窓ガラスの破片や屋根瓦などの落下物に注意して、近くの空き地などへ避難する。
商店街・ビル街にいたら
- その場に立ち止まらず、カバンなどで頭を保護して近くの空き地などへ避難する。
- 建物や自動販売機、ブロック塀、電柱のそば、ビルの壁際などから離れる。
- 垂れ下がった電線には近づかない。
電車などの車内にいたら
- 急停車することがあるので、つり皮や手すりなどにしっかりつかまる。
- 途中で止まっても、非常コックを開けて勝手に車外に出たり、窓から飛び出したりしない。
- 乗務員のアナウンスに従って落ち着いた行動をとる。
海岸・がけ付近にいたら
- 海岸や河川の付近の場合は、ただちに高台などに避難し津波情報をよく聞く。(警報・注意報が解除されるまで絶対に海辺などの低地には近づかない)
- 山、急な傾斜地、川べりでは、なるべくがけから離れた場所に避難する。
車を運転していたら

- 地震を感じたら、徐々に速度を落とし、道路の左側に寄せてエンジンを切る。
- 揺れがおさまるまで車外に出ず、地震情報をカーラジオで聞く。
- 車を離れるときは必ずキーはつけたまま。ドアロックもしない。
- 車検証や貴重品は携帯する。
地震による火災に備える
火災から身を守るために
火災で最も怖いのは想像以上の速さで広がる煙です。煙には有毒ガスが含まれますので、姿勢をできるだけ低くして、濡らしたタオルなどで口と鼻をおおい避難しましょう。また、火災を発見したときは、大きな声で助けをもとめ、すばやく初期消火にあたりましょう。
火災避難のポイント

- 天井に火が燃え移ったときが避難の目安
天井に火が燃え移ると、火災は一気に拡大します。 - 炎の中では、ちゅうちょは禁物
濡れたタオルで頭をおおい、一気に走りぬけましょう。 - 煙の中では姿勢を低く
煙の中では、姿勢を低くして濡れたタオルで口をおおい、床をはうように避難しましょう。 - 服装や持ち物にこだわらない
煙の勢いは想像以上に速いものです。できるだけ早く避難しましょう。 - 災害弱者の避難を優先に
お年寄りや子供などを優先に避難させてあげましょう。 - いったん逃げ出したら戻らない
たとえ貴重品などを持ち出せなくても、再び中には戻らないでください。
地震による津波に備える
津波から身を守るために
津波から身を守るためには一刻を争います。津波の伝わる速さは時速数100キロメートルにもなる場合があり、津波が見えてから逃げても間に合いません。強い地震や長い時問の揺れを感じたら、ただちに海岸や河川から離れ、急いで安全な場所に避難しましょう。
津波避難のポイント
- 海岸で強い揺れを感じたら避難
海岸で強い揺れや長い時間の揺れを感じたら、直ちに海岸から離れ、津波緊急避難場所に避難します。決して海岸に近付かないようにしましょう。 - 河川付近からすぐに離れる
津波は河川を遡上して浸水してきます。河川付近は大変危険ですので、すぐに避難を開始してください。 - 津波警報・注意報が出たらすぐに避難
ラジオやテレビなどから正しい情報を入手します。「津波注意報」や「津波警報」が発表されたら、ただちに津波避難所に避難します。 - 火の元の確認
避難する前に、火元の確認をしましょう。ガスの元栓を閉め、電気ブレーカーを切るのも忘れずに。 - 身軽な服装で
身軽な服装で避難をしましょう。軍手や底の厚い丈夫な靴、ヘルメットや防災ずきんも役立ちます。 - 荷物は最小限
避難する際の荷物は必要最小限にし、日頃からリュックサックに入れて準備を。 - 徒歩で避難
必ず徒歩で避難します。車は厳禁! ちょっとした原因で渋滞し、津波に巻き込まれてしまいます。 - お年寄りや子どもを守ろう
お年寄りや子どもは、手をしっかり握って避難しましょう。ご近所どうしで声をかけ合い、助け合いましょう。 - 遠くて高い場所へ避難
できるだけ海岸から遠くて高い、安全な場所を選んで避難しましょう。 - 自宅へ戻るのは警報・注意報解除後
自宅へ戻るのは、必ず「津波注意報」や「津波警報」が解除されたあとにしましょう。ラジオなどで正しい情報を入手しましょう。
この記事に関するお問い合わせ先
防災安全課 消防防災係
〒515-0332 明和町大字馬之上945番地
電話番号:0596-52-7110
ファックス:0596-52-7133